|
パソコン心電計:ECG Explorer 500A(500X1,500X2)のページ(医療関係者専用)
+iPhone、iPad用ワイヤレス解析機能付心電計 smart ECGのページ
HOME > パソコン心電計:ECG Explorer
最終更新日:2023年01月03日
木村@熊本市@日本循環器学会認定循環器専門医(+学会認定内科専門医)です。 [当院のHPトップ]
熊本市の無床診療所:清水まんごくクリニックで診療を行っています。
心電計業界では、フクダ電子(株)・日本光電(株)のユーザーが多く、他社の心電計の情報が乏しいと感じています。
このHPをご覧の皆様に、当院が平成22年末に購入した、三栄メディシス(株)製のECG Explorer 500Aの使用感・
個人的印象を”情報提供”してみたいと思います。医療関係の皆様のご参考になれば幸いです。
なお、平成25年春に、ECG 500Aは、X1・X2にバージョンアップしました。でも、基本性能は変わりません。
耐久性をみるためにも、バージョンアップせず、このまま500Aを使い続ける予定です(トラブルないですし)。
また、同じ会社がiPhone、iPad専用心電計:smart ECG も発売しています。これについても書いてみました。
新着情報・・・購入後のエピソードを最後記に記載しています。この行をクリックです。
*2023/01/03追加:Windows 10、Win11パソコンにデータを移行できるか検討した・・・成功だ!
*2022/07/04追加:後継機種の500X1、500X2への機器更新のDM来た。このまま500Aで行くぜ!
*2022/04/02追加:胸部電極が劣化したので、注文購入した。すばやく入手できた。
*2020/03/10追加:プリンタをA4レーザープリンタに変更した。より便利となった
*H29/02/05追加 :心電計のコードは耐久性のあるものに変更になったそうな。めでたし。
*H29/02/04追加 :心電計の電極コードが劣化したので、”三本型心電誘導コード”をネット購入してみた
*H28/01/01追加 :安価なLiteが発売中。中古も販売している。
*H27/09/20追加 :当院で購入して5年弱経過。全くトラブルなし。
*H26/12/14追加 :当院で購入して4年目経過。全くトラブルなし。
*H26/12/10追加 :同社がH26/12/01より”iOS対応心電計”を発売している
*H26/01/20追加 :タブレット(iPad、アンドロイド端末)での心電計を発売。まずはアンドロイド端末のみ。
*H25/05/20追加 :「ECG Explorer 500X1、500X2」発売:サイズがコンパクト化、Bluetoothによるパソコンへのワイヤレス接続可能。
*H25/04/30追加 :購入後3年半でトラブルなし、心電図自動解析(コンピューター診断)について記載する(その2)
*H24/06/25追加 :開発元が自律神経機能ソフトをオプション発売する模様 → 本体+追加3万円で発売となっています。
*H24/06/25追加 :開発元が自律神経機能ソフトをオプション発売する模様。
*H24/06/20追加 :Late Potential(加算心電図による心室遅延電位測定:LP)測定機能を追加導入・・・非常に期待しています。
*H24/05/01追加 :心電図自動解析(コンピューター診断)について記載する・・・十分、使えますね。
*H24/02/20追加 :開発元が「加算平均心電図による心室遅延電位測定」機能の追加のアナウンス
*H23/09/20追加 :500A製造の三栄メディシスのユーザーフォーラムに登録した・・・こりゃいい。トラブル回避できます
*H23/07/20追加 :(擬似)マスター負荷試験を実施・・・うまく評価できました
*H23/07/16追加 :四肢電極のプラスチック部分が割れてしまった・・・でも、大丈夫
*H23/04/30追加 :500A製造メーカーの三栄メディシスが、販売価格を14万8千円に改定・・・激安ですね。
まずは、当院での現状:当院では下図のようにして使用しています。
今までの心電計架台を流用。ノートパソコンを置いて、荷物固定用ベルト(緑色・・・現在は黒色)で固定。
ノートパソコンの右側にUSBハブをつけて、パソコンの後ろに、USB経由でセキュリティーキー、プリンタ、
そして500A本体を接続しています。パソコンの下には、インクジェット式プリンタを置いています。
なお、ベルトで固定してあるのは、たまに、このパソコンを講演会でのプレゼンテーションに持ち出し使用することが
あるためです。フリーソフトのOpen Office Orgをインストールしてあり、
この中のプレゼンテーションソフト(Impress)を講演会で使用しています。Power Pointライクで十分な使用感です。

さて、平成23年2月現在、日本ではパソコン上で作動する心電計としてスズケン(GE製)と三栄メディシス製などが
あります(他にもあります)。三栄メディシスは、ECG Card(アメリカ:ECG Diagnostic社製)を販売していましたが、
平成22年秋にECG Explorer 500Aを新発売しています。すべてパソコンのUSB端子に接続して使用します。
タイミング良く(?)、当院で使用していた心電計が寿命を迎えましたので、新発売の500Aを購入してみました。
平成23年3月時点で三栄メディシスに掲載していない情報も記載しました。
なお、24年3月現在、ソフトのインストール&使用マニュアルがダウンロードできます。ここです。
スズケン製(GE製造)の心電計も、比較的安価で入手できるかもしれません。最後部に資料をつけます。
まず、その前に専用心電計でなくパソコンを使用するメリットは:
○単価が安くなる:
パソコンなら印字はプリンタまかせ、画面・ネットワーク・データ保存はパソコンまかせ
専用の機械ユニットで心電計を製造するのでなく、汎用パソコンを使用するので、総じて安価となります。
○故障に強い、故障時もすみやかに使用可能:
経年変化で心電図用紙のローラーが滑ったり、ボタンが押ししぶくなったりします。
パソコン上の心電計なら、安価なプリンタで新規交換、10万円以下のパソコンを新規購入などで継続使用
できます。緊急時に他のパソコン・プリンタにつないで、という手もありますね。
○ID、名前の登録が容易
パソコン内にデータ保存する時に、パソコンのキーボードを使用してIDや姓名を登録できます。
データファイリングする時に便利です。
○ネットワークに強い、データ保存が便利
現在のパソコンなら100M〜1Gb/sの高速でネットワークが組めます。心電図印刷をネット上のプリンタで、
ということも可能でしょう。データ保存もネットワーク上の他のパソコンやデータサーバーに転送したり
USB端子からUSBメモリに保存して他のパソコンへ、USB端子から外付けハードディスクへ、も可能ですね。
○印刷が熱転写用紙でない
ご存知のように、熱転写用紙は数年後には印刷が薄くなり判読しづらくなります。パソコンプリンタ方式なら
A4用紙に直接印刷しますので印字の劣化を防ぐことができます。また、”心電図用紙の在庫”を考えなくて
すむこともメリットです。
○往診や院内緊急時に持ち運べる
ノートパソコン(ネットブック)と本体(数百グラム以下)があれば心電図がとれます(100V電源が必要かも)。
画面で確認してパソコン内のハードディスクやUSBメモリに波形を保存。あとで印字・紹介先へ添付などが
可能です。数Kgの心電計を担いでの移動はちょっと大変です。ノートパソコン+500A+セキュリティーキーを
持って行けば心電図がどこでも取れる、というのは魅力的です。
*開発元の契約条項がどうなっているかはっきりしない点がありますが、ソフト自体は複数のパソコンに
インストールできます。しかしセキュリティーキーがないとソフト自体は立ち上がりません。逆に言えば
診療部門や病棟のパソコンにあらかじめ500Aソフトをインストールしておけば、緊急時には500A本体+
セキュリティキーを持ってくるだけで心電図をとることができます。また、普段、持ち運びして手元に
いつも置いてあるノートパソコンにソフトをインストールしておけば、緊急時に500A+セキュリティキーを
持ってくることで心電図が取れる、ということになります。
ちなみに、今回、当院で購入したものは:
ノートパソコンはDELL製Vostro 1015(Windows 7、32ビット、画面15.6インチ、購入価格 約4.5万円)
HP製インクジェットプリンタ(黒色独立インク。単色で印刷モードで使用)です。
低価格パソコンでしたが全く使用に支障ありません。
*ノートパソコンのUSB端子に接続すると、端子部が横に飛び出して横幅を取ることになります。
また、うっかり手で触ったりしてUSB端子から外れたり、端子の破損する危険性が気になりました。
ノートパソコンのUSB接続部がパソコン後面にあれば大丈夫でしょうが、そんな機種は少ないのでは?
また、500A本体、セキュリティーキー、プリンタ接続でUSBを3つ消費します。
そこで、パソコンのUSB接続部がL字型に折れ曲がり横幅を取らないUSBハブをつければ、となります。
バスパワータイプ(パソコンからの電力で作動)で大丈夫か、セルフパワータイプ(電灯線から電源を得る)が
必須なのかも気になります。
・・・試してみました。上記DELLパソコンに3ポートタイプのバスパワータイプUSBハブを接続し、
上記3つを接続、実際にECGを取り画面停止して印刷をしてみました。結果、問題なく作動しました。
端子部はL字型に曲がるためスペースも取らず、うっかり手に引っ掛けることもなくなりそうです。
今回の使用ハブは、バッファロー製(BSHT303:延長コード30cmタイプ、コネクタ接続部が90度曲がる)でした。
パソコンによってはUSBへの電力供給が不十分、延長コードが長いと電圧低下のために作動不全などがあるかも
しれません。自己責任でお願いします。
*平成23年4月追加:インク使用量を計測してみました。500Aの印刷モードは白黒のみ。プリンタインクは、
HP社純正”178XL スリム増量”です。結果、約75枚(A4版)=75名程度の印刷ができました。
うーーん、この印刷枚数が多いのか少ないのか、、、。レーザープリンタならワントナーで数千枚印刷
できますので、インク交換(トナー交換)を考えるとレーザープリンタのほうが有利となりますね。
なお、この”スリム増量”は、通常の”増量”タイプよりもインク量は多くないので、”増量”タイプを
使用できる機種なら、よりコストパフォーマンスが良くなるでしょう。ランニングコスト下げるために、
インクジェットプリンタインクを互換インクにする、リサイクルインクにする、などの手もあり。
LANを組んで院内のLAN上のレーザープリンタに印刷する手もあり、です。
皆様でいろいろとお考えください。
さて、ECG Explorer 500A の印象、機能(H23年初め、Version 1.002)は
ご注意:今までアナログ心電計を使用していた者の個人的印象です。その点をご理解ください。
○シンプルで使いやすい
機能がキーボードのファンクションキーに割り振られている(マウスでも指定可)。しかも、トグル(表示速度:
12.5/25.0/50.0mm/s、筋電フィルター:30/40Hz、ドリフトフィルター:0.05/0.15/0.25/0.50Hz)になっている
ので、操作も簡単だし修正も容易。IDや名前などの入力ではキーボード入力が必要だが、操作はシンプルで、
導入はきわめて容易だ。
○ドリフト除去機能がしっかり
被験者に動いてもらったが、ドリフト機能がしっかり働いてキレイな心電図がとれました。筋電フィルターを
画面で確認しながら変更できるのも便利です。
○マウス右クリック:画面計測機能にビックリ
心電図画面でマウスを右クリックして移動(ドラッグ)すると、移動分だけ四角形が表示されます。マウスから
指を離すと”○○mV、○○m秒、心拍換算○○回/分”と表示されます。R波の高さを測ったり、RR間隔を確認
するのに便利です。なお、右クリックでJPEGとPDFファイルへの保存するかどうかのメニューも出ます。
○印刷パターンが多い
縦、横で5通り(1列12ch、1ch、3ch、6ch表示など)ずつで合計10通りの印刷可能。デジタル保存なので
印刷したあとに、別の形式で印刷することも可能。・・・通常は6ch2列印刷で、不整脈時に1ch長時間印刷と
すればいいか、と思った(施設によって、この辺は違いますね)。
○複数台のパソコンにインストール可能のようだ・・・セキュリティキーがあるが、、、
セキュリティキーが1つ同梱しており、それをパソコンのUSBポートに差し込むことでソフトが作動します。
このキーは普通のUSBメモリと同じデザインだが、中に専用LSIが組み込まれているような気がします、、?
電子認証??まあ、500Aの本体がないと心電図はとれないので、セキュリティキーでの認証は不要な気もするけど。
しかし、複数のパソコンにソフトをインストールしておいて、いざという時に非常用パソコンに500A本体と
セキュリティキーをUSBポートに差し込んで、即、使用とできると便利ですね。
○保存データを呼び出し、感度・速度・印刷パターン・印刷時間帯の変更が可能
ちょっと感激。過去データを呼び出してファンクションキーを押すと、心電図表示の感度・速度が変化します。
画面下には水平スクロールバーがあり、これをマウスで動かすことにより保存したおいた時間帯の任意の時間を
画面表示したり印刷したりできます。また、上記の”マウス右クリック”機能が保存データでも使用できる
ことにも感激しました(デジタルデータなので、当たり前といえば、そうなんですけど、、、)。
○保存ファイル形式は・・・
専用ファイル形式で140Kbyte、変換したPDFファイルもJPEGファイルもファイルサイズは930Kbyte程度でした。
思ったよりJPEGファイルサイズが小さくなかったのですが、表示してみると非可逆圧縮形式でノイズがある
はずなのですが全く気になりません。JPEGでも画質優先でファイル化しているためでしょう。ちらっと
見るならJPEG、PDFリーダー立ち上げての閲覧ならPDFファイル、となるのでしょう(か)。RS-BASEなどの
画像ファイリングソフトでは、このJPEGないしPDFファイルを登録しておいて、画面表示となるでしょう。
”専用ファイル読み出し専用ソフト”があると便利な気もしますが、パソコン内にソフト(実行ファイル)が
増えるのも・・・。現在のやり方でよいのでは、と(も)思います。ちなみにZip化したら
どちらも495Kbyte程度になりました。
○画面解像度が低くても使える(メーカー保証外です。推奨しません)
メーカー推奨の”画面解像度は1024X768以上”だが、無理やり画面解像度を800X600して立ち上げてみた
・・・使えます。画面の右側が切れてファンクションキー[F11]、[F12]が見えませんが、作動はします。
このソフトは立ち上げ時に画面の縦解像度を計測してV1〜V6誘導がきっちり表示できるように自動調整して
画面表示するのですね(確認しました)。縦解像度600では、V1〜V6間が狭くてQRSが重なってしまいましたが
心電図感度を10→5m/mVに表示変更で判読できるほどにQRSを分離することができました。
○ソフトのWindowを動かすことはできない
このソフトは立ち上げると画面いっぱいに広がりますが、タイトルバーがないために最小化や画面内移動は
できません。複数のソフト(←CPUパワーを使用するものは並行使用は良くないでしょう)やイクスプローラーを
立ち上げているときには、Alt+TABキーないし、タスクバーをマウスクリックしての切り替えとなります。
*試してみたところ、Window styleを無理やり変更してタイトルバーを発生させると、それをマウスでつかんで
ソフトのWindowを画面内で移動することができましたが、あまり意味のないことですねえ。
*おまけ:インストールすると、”mdb”という拡張子のファイルが一個できます。
Microsoft Access形式のファイルです。パスワードが必要で、そのままではAccessソフトを持っていても
開くことができません。そこで、パスワード解除ソフトで解除して閲覧してみました(←こんなことやっちゃダメ。
ネット上の”Accessパスワード解除ソフト”には、トロイの木馬などウイルスが組み込まれているものがあります。
ご用心です。正規ユーザーは、三栄メディシスに問い合わせると、パスワードを教えてくれます)。
中味は、6つのテーブルのみ。ECGデータの保存path(ハードディスクのどこに保存してあるかのパス)や
患者名・年齢・IDなどのテーブル、ECG診断名のテーブル(日本語・英語・中国語があり)などがあるのみ、、、。
わざわざ見るほどのものではありません。
なんでパスワード付きのAccess形式のデータベースにしたのかしら?確かに、ECG解析アルゴリズムを変更して
ECG診断名を追加した時など便利ですからねえ。また、Mdb形式なら、C++、C#、Delphi、VBAなどの言語でも
アクセスできるのでプログラムも開発しやすいでしょう。Mdbファイルは最高 2Gバイトの上限があるけど、
このmdbファイルに保存するのはECGファイルのpathや患者名などの情報のみ・・・数万人を登録しても
2Gバイトになることはありませんね。安心です。
ただ、使用途中でECGファイルの保存場所を変更する(CドライブからDドライブへ、など)しても
大丈夫なのですが、Cドライブ中のECGファイルをDドライブのECGファイルと同じフォルダーに移動するなどすると、
500A Explorerでは移動後のファイルを読むことができません(ファイルパスは以前の位置を登録してあるので)。
上記の場合の対応策は、専用ソフトを開発してもらう、パスワード解除でテーブルをパソコン画面に表示し、
クエリないし手作業でパスを書き換え、、、かしら?
現状では、ユーザーは、ECGファイルの保存場所は500A使用開始前にしっかり考えておいたほうがよい、となります。
現状(H22年末、Version 1.002)での機能不足点(平成23年3月追記):
○現状では、RR間隔変動を測定して自律神経機能(SD、CVなど)を表示できません。
糖尿病専門医や神経内科専門医の先生方は、もの足りなく思うでしょう。でも、一般的なニーズでは
SD値やCD値を測定することはないでしょう。”不要”といえば不要ですねえ。
*平成23年3月時点での三栄メディシスのお話では(電話で直接聞きました)、心拍変動(自立神経機能)や、
late potential計測ソフトも開発中だそうです。Late potential(LP)とはマニアックな感じもしますが、
実臨床でLPが計測できるなら、外来・病棟患者さんのリスク管理やリスクレベル推察に非常に有用かも
しれません。
*ついでに:インストールすると、”VCG”というフォルダーも自動で作成されます。フォルダー内はカラですが、、、。
VCGって、ベクトル心電図ですよねえ。温故知新!!21世紀になって、もう一度、VCGしましょうか!
循環器専門医師の”血”が騒ぎますね (^_^)。もしかすると、将来は、VCG表示ソフトが同梱されるのかも。
○時系列での閲覧が不能
同一個人の複数回の心電図を閲覧できると便利ですが、、、。
でも、これってアナログ心電計にもこんな機能はなしです。”贅沢な注文”なのかもしれません。
また、三栄メディシスでは、”ソフトをいずれ開発する”とアナウンスしています。
http://pc-ecg.com/ecg_user_honma.html
ご指摘のあった心電図波形の取り込みや、IDなどの患者情報の取り込みのできる心電図閲覧用のソフトは、
今後開発をしていく予定となっております。そのソフトの中で、心電図波形の時系列比較など、
波形データの活用ができるようにしていきたいと考えております。
・・・将来にご期待!、というところですね。
○マスター負荷試験機能がない
”今の時代にマスター負荷試験は不要(危険)”、”いやいや、なかなか便利な検査だ”とのご意見がある
でしょう。総じて”マスター負荷試験機能”がなくても問題ないと思います。どうしてもなら、
安静時心電図を取ったあとで、運動負荷を行い、再び経時的に心電図をとってST、T部分を比較すれば
いいでしょう。
結論として:
私は購入してよかった、と思いました。”長く使用できるかは長年使用してみないとわからない”という
耐久性の問題がありますが、メーカーが”5年保証”としていますのでこの点でも(まあ)安心できるのでは、
と考えています。
なお、このHPは、500Aを推奨・購入強要するものではありません。医療機器の選定・購入にお困りの方々の
ご参考になればと作成してみました。ご参考になれば幸いです。なお、ご購入は自己判断・自己責任でお願いします。
さて、ご参考までに検討した図を以下に供覧します。
デスクトップパソコンに一時的にソフトをインストールしてセキュリティキーをUSB端子にセット。
ECGを取ってファイリング。画面解像度を変えたりして保存データを呼び出し画面表示。
画面キャプチャーして以下に供覧です。
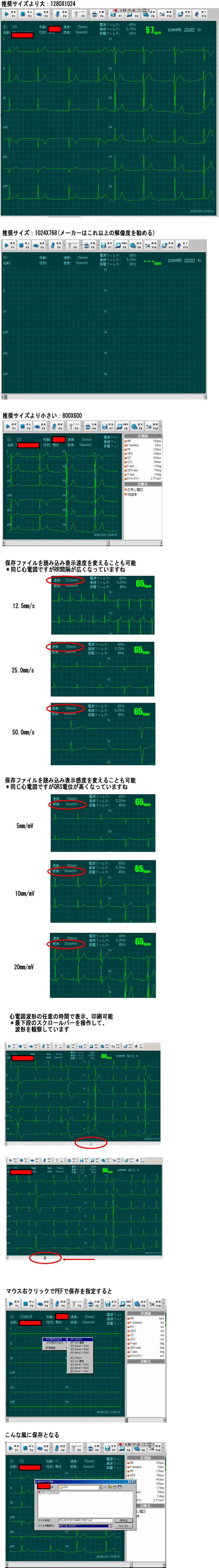
新着情報:
*2023/01/03追加:Windows 10、Win11パソコンにデータを移行できるか検討した・・・成功だ!
2023現在使用しているノートパソコンは、Microsoft社のサポートが終了したWin7。
ノートパソコン自体も2010年に購入したもので、突然のHDDの作動不良〜パソコン立ち上がらず〜ECG計測不能が恐ろしい。
※フリーソフトとCrystalDiskInfoで現状を確認した:内蔵HDDは”正常”で合計作動時間は丸12年間で9600時間・・・ECG計測専用なので
長時間のHDD通電はないということだ。しかし、購入12年目で電源の突然の作動不良なども心配。最新OSへの移行を以下、検討した。
〇手持ちのWin10ノートパソコンに2010年に購入した当時のECG ExplorerソフトCD-ROMからインストールを開始する。
でもCD-ROMの中身を見ると、Xp、Vista、Win7用のインストールSetup.exeしかない(当時だから当たり前)。しかたないので、Win7用でSetup開始。
しかし、Win10 OS下ではセットアップが中断する。やむえず、セットアップソフトの本体:ECG Explorer500A.msiでインストールしようとするもエラー。
”互換モード”、”管理者権限”でインストールも試みるが失敗。いろいろと強引にインストールする方法もあるのだろうが、無理せずに
本家:三栄メディシスのHPを確認する。
〇本家:三栄メディシスのHPのソフトウェアのDownloadページを見る: https://www.pc-ecg.com/1306/dl/index.html
ECG Explorer 500 Ver1.0.1.20.zip(95.5MB) ダウンロード 作成日 2022/01/14
ダウンロードボタンからZipファイルのダウンロードを行い、解凍してご使用ください。
インストール方法は同封の「インストールマニュアル」をご参照ください。 ・・・さっそくDLしてみる。
DLしてみると、”ECG_Explorer500X_1.0.1.20”とあり、旧型500Aでなく、現行機種の500X1、500X2のソフトとなっている。
当院の500Aに対応しているか不安になるが、マニュアルを読むと”500Aのソフトに追加して、このソフトをインストールすると、、”の文面あり。
つまり、”本体500A+500Aソフトを使用している状態”でも””ECG_Explorer500X”のソフトが使えそうだ!、
また、マニュアル最後尾の”仕様について”では、X1、X2とともに500Aの記載もあるので、旧型ハードの500Aにも対応していますね!
と自分を納得させてインストール開始。
USBメモリからWin10ノートパソコンでインストールでまったく問題なくインストールを終了した。
※このソフト内には”アンドロイド心電計”(アンドロイドOSでのタブレットを心電計にするソフト)のフォルダーがあり、ソフト群がそろっている。
また、”アンドロイド心電計PCとの同期方法.pdf”なる解説書も同梱しており、往診先でのタブレットで心電図を保存、医療機関内で
データ統合保存をする方法も解説している。なお、アンドロイドタブレットでのECG確保には、500X1(USB端子による有線のみ)でなく、
500X2(Bluetoothによるワイヤレス方式も対応)が必要だ。だって、タブレット使用時には、Bluetoothを使って心電図通信をするからだ。
〇当院のWin7パソコンデータを新規インストールしたWin10パソコンにコピーしてみる。
心電図データファイル(個々のECG波形は、1心電図そのまま1つファイルとして保存)は、初期設定ではc:\NetECGDataフォルダー
データベース(自動解析病名などもろもろ)は、 NetECG.mdbにある(500AとX1、X2では保存フォルダーが異なることあり)。
Win7パソコンの”NetECGDataフォルダー”をまるごと、Win10パソコンに上書きコピー(12年間4800ファイル 1.1Gbyteあり)。
NetECG.mdbは、Win10マニュアル記載の通り、500AのWin7では異なる場所にあったので探し出して上書きした。
※”上書き”しなかったほうが良かったかも、、、。(情報不足でよくわからない)
〇Win7のUSB端子に接続しているインストールキー(ドングル:これがないとECGソフトが立ち上がらない)をWin10パソコンに接続。
過去データを呼び出してみるとキチンと表示。また、新規に心電図をとってみたが今まで通り実施できた。
・・・これで新しいパソコンへの移行が容易に可能なことが確認できた。
上記のように、”Windows 10、Win11パソコンにデータを移行できるか検討”して成功した。
メーカー:三栄メディシスのサポートもありがたいですね。パソコンと連動する医療機器が増えたが、OSのバージョンアップに伴い
”Win7とはデータ操作ができますが、新しいOS(Win10など)ではできません。新しいハードを買ってください。お安くしますよ”と話がでることは
しばしばです。古いOSのサポートが難しいこともあるでしょうが、ハードとしての医療機器を購入した場合にOSがバージョンアップしても
サポートしていただけるとありがたいです。”ECG Explorer500シリーズ”は、2010年の発売当初は、Xp、Vista、7であったが、今回検証のように
Win10、Win11でも同じハードが作動する。ECGの過去データの移行も容易・・・長期間、使用できますね。
*2022/07/04追加:後継機種の500X1、500X2への機器更新のDM来た。このまま500Aで行くぜ!
同社から”ご購入11年経過しました。ご使用ありがとうございます。後継機種の500X1、500X2に変更しませんか?定価の2/3でOKですよ”
とダイレクトメールが来た。
うーーん、お得な感じあり。でも、当院では購入11年+α。チャレンジ精神で初期型500Aを継続使用+レポートしていきます。
この11年間のトラブルは、誘導コードが劣化して1度交換(むしろV1-V6が1ラインの一本型心電誘導コードに変更できてありがたい)、
数年前と今年に電極ゴムを交換したのみ。本体はまったくトラブルなし、です。Windows 7のデル製ノートパソコンもトラブルなし、です。
昔、使用していた熱転写式ECG用紙を使用せず、コピー用紙に印字なので、保存・閲覧に便利です(注:ECG波形はデジタル保存もできます)。
*2022/04/02追加:胸部電極が劣化したので、注文購入した。すばやく入手できた。
胸部電極のゴム部と金属部が経年変化で緩んできました。どの心電計を使用していても起こる現象です。
同社のHPからネット注文です。以前は6色カラーだったのが全電極単色ネズミ色になっていますねえ。
6ケで4400円で注文すると送料+1000円。もしかしてと2セット8800円で注文すると送料なし、となりました。
・・・うーーん、2セット注文しました。驚きました。48時間で九州熊本まで宅配で届きました。早かったです。
*2020/03/10追加:プリンタをA4レーザープリンタに変更した。より便利となった
長らくHP製のインクジェットプリンタを使用していましたが、生産中止+それに伴いインクタンク自体が生産中止となり
使用できなくなりました。後継として、1)インクジェットプリンタ、2)レーザープリンタ、を検討。
インクジェットプリンタの欠点:頻回のインク交換(HP製では75枚/タンク。そのたびにタンクの交換+色調合わせなどの
初期設定が必要)・・・診療中にこれが発生すると面倒。インクタンクが高価(互換品では製品安定性に欠ける)。
それに対してレーザープリンタは:トナー交換頻度が公式では2000枚前後と長い、印字品質がよい、のがメリットです。
心電図印刷なのでカラー機能は不要。A4レーザーなら現在は1万円前後で購入できます。使用電力はレーザーが大きいけど
頻回に使用しないので問題なし。最近では大タンクのインクジェットプリンタも発売されているけど、本体自体が高価+
プリンタヘッドの清掃の手間が発生する・・・ことも考えるとレーザープリンタの方がベターですね。
ということで、キャノン製(他のメーカーでも問題なし)のシンプル+安価+コンパクトなレーザープリンタに変更しました。
※容易に何枚もきれいに印字できる・・・ということで来院者に心電図コピーを渡す頻度が増えました。
十分な説明+情報公開・・・という点で、大量印刷が容易なレーザープリンタのほうが便利ですね。
*H29/02/05:心電計のコードは耐久性のあるものに変更になったそうな。めでたし。
三栄メディシスでは、購入ユーザーに”PC-ECGユーザーフォーラム”というHPを提供しています。一般ユーザーがメディシスの開発部と
ダイレクトに相談ができるネット上掲示板、というところです。そこに、”心電計のコードの材質は変化したのでしょうか?”と質問してみたら、
「熱可塑性ポリウレタン(TPU) に変更しました。 従来品は塩化ビニール製です。耐久性は増しています。
良質な製品をご提供できる様、頑張っております。」(原文ママ)・・・のお返事投稿が開発部からありました。
おお、やっぱり材質が変更になっているのですね?初期型コードと比較して、02/04購入のものは確かに(少し)柔らかくなっています。
長く使えるとありがたいなあ、と思います。
ついでに:他の医療機器メーカーと異なり、三栄メディシスは上記(PC-ECGユーザーフォーラム)のような形でユーザーとコンタクトを
とれるようにしています。疑問に思ったことをネット経由で質問〜解決できる方法をメーカーが提供する姿勢はいいなあ、と思います(上から目線??)。
*H29/02/04追加:心電計の電極コードが劣化したので、”三本型心電誘導コード”をネット購入した。
購入して5年半ほどしてきて、心電コードが劣化して縦割れを起こしてきた。ビニールテープで補修して使っていたが、
あちこちが割れてきたので更新することにした。三栄メディシスでは、付属品(パーツ・アクセサリー)のみでも購入可能。
購入数年後でも、パーツ単独が購入できるのはありがたい。三栄メディシスの心電誘導コードは、4種類ある:
従来型(胸部誘導6本+獅子誘導4本)、一本型心電誘導コード:胸部V1-V6が1つ+四肢誘導4本、
三本型心電誘導コード:胸部V1-V6が1つ+四肢誘導2本、胸部V1-V6が1つ+四肢誘導4本(心電誘導コード・ミニ:解説)がある。
なお、胸部誘導の6本コードを、1本にしたのは実用新案登録済だそうな。
どうせ購入するのだから、三本型心電誘導コード(胸部V1-V6が一つ+四肢誘導2本)を購入してみた。印象を記す(イラストはここ):
従来の10本の電極から、胸部1本+左側1本、右側1本となった。従来型では、胸部電極誘導の6本を持ち上げるとクルクル回って絡まりがちだったが、
三栄の心電誘導は胸部誘導が1本になっているので絡まることはありえない。未熟なスタッフが実施時や慌ただしい時に胸部電極つけ間違えするリスクが
あったが、この電極コードは1本だからつけ間違いもありえない。
結果、心電図を判読する時に、”おいおい、電極つけ間違えでは?”と想像・鑑別しなくていいのは、非常にありがたいことだ。
また、普段は心電計を使用しない 施設(整形外科の病棟など)では、不慣れなスタッフが安心して電極を胸部にセットできるので便利だろう。
欠点として、電極間のループを巻いている部分に重量があるので、設置した電極が引きずられて外れるケースがあったが、
この場合、電極ループと体表面の間にタオルなどを入れて、電極ループの荷重を支えることで電極は外れなくなった。問題なく使えている。
四肢誘導は、4本コードから左右の2本コードになったが、あまりありがたみは感じなかった。四肢誘導の緑コード(足電極)と黒コード(不感電極)は
理論上、左右交換しても問題なし。問題は左手コード(赤)と右手コード(黄)を間違えることである。
従来型でも今回購入品でも、心電計操作者が左右を取り間違える可能性はあるので、この点で胸部誘導ほどの”電極つけ間違え回避”はできない。
”電極つけ間違え回避”のために購入するなら、一本型心電誘導コードでも三本型心電誘導コードでもOKと
考えた(だから三栄は2種類とも販売しているのか?)。ただ、三本型のほうがスッキリ感はある。当院では、心電図専用ベッドがあるので、
左側四肢電極はベッドと壁の間に置いておき、ベッドの頭側に胸部電極コードと右側四肢電極を2つの小山にして置いてある。
受診者を寝かせて、電極の色など考えずに心電図が取れるようになった。便利になったと思うし、(電極つけ間違いという)リスク管理になったと思う。
*H28/01/01追加:安価なLiteが発売中。中古も販売している。
Windows OS用心電計、iPad用心電計ともに、Lite版が販売してます.また、リファービッシュ版、中古旧番ECG 500A も販売中。
通常版、リファービッシュ版、Lite版は、X1で、19万8000円、15万8400円、 9万2593円。
X2で、29万8000円、23万8400円、13万7037円。
中古旧番のECG 500A(当院使用中)は、8万8000円でも販売中・・・3万円で同社が下取りしたものですね。
また、iPad用心電計 smart ECGも、クラウド機能のみを外したLite版が13万円安い 18万5185円で販売中。
医療機関内のみで使用、往診・訪問診療からの帰院後にケーブル(など)で保存・印刷ならば、安価に購入できます。
後日、差額の支払いでLite版から通常版にバージョンアップもできるそうな。
2015/12/31まで、500台限り、となっているけど、しばしばキャンペーンで同様の価格でHP上で販売しているので
ときどきHPをチェックしてみるのみいいですね。
*H27/09/20追加:当院で購入して5年弱経過。全くトラブルなしです。
*H26/12/14追加:当院で購入して4年目経過。全くトラブルなし・・・本製品はX1、X2にバージョンアップしていて
当院の500Aは置いてけぼり状態がちょっとさびしい。ネットでは、旧タイプのECG 500Aが、
同社が下取りを行い、「2年保証の認定中古心電計」として再販売中。
H26/12/10現在で8万8000円とは激安か。
実際、老健施設など「めったに心電図を取らないが心電計が建物内にあるとありがたい」、
「眼科、耳鼻科で心電図を取ることはほとんどないけど院内には欲しい!」などの場合にはベストチョイスか。
*H26/12/10追加:同社がH26/12/01より”iOS対応心電計”を発売している。商品名は「smartECG」。
このHPには、会社名:三栄メディシスがない。でもコンタクト先の電話番号は、(H26/12/10時点で)同社のものだ???
・・・同社のパスワード付き掲示板:”PC-ECG ユーザーフォーラム”を見ると、
心電開発事業に埋没するため、新たな会社を設立しました。ECGラボといって、心電図(計)をより深く研究し、
自らの不整脈の解析、そして未来の心電図の予知といった、技術者の見地から心電図学に進んでみようと考えています。
・・・とあり、(形上は)三栄メディシスとは異なる会社なのですね。HPのデザインも似ているし、なにより心電計電極が
500X1、X2と同じものですもの。うーーん、同社の意気込みを感じますね。
*H26/01/20追加:アンドロイド端末で心電図を取ることができます。外来診療のみならず、病棟、往診、在宅診療でも便利ですね。
三栄メディシスのHP参照を。
*H25/05/20追加:ECG Explorer X2発売:よりコンパクト、ワイヤレス可能、ミネソタ解析可能となっています。下取りもありますね。
*H25/04/30追加:購入後3年半でトラブルなし、心電図自動解析(コンピューター診断)について記載する(その2)
平成22年12月に購入してから全くトラブルなし、です(下記H23/07/16記載の電極プラスティックが割れた以外なし)。
ほぼ毎日使用していますが、作動は購入初期と全く変わりなし。下記H23/07/20記載の方法で、運動負荷心電図としても
使用しています。
ついでに、心電図自動解析について再度考察:当院に健診でWPW症候群を指摘された方が受診となりました。
たしかに心電図はR波の直前にスラーがあり、典型的なWPW症候群です。
健診結果を見ると、2年前は「陰性T波」、1年前は「ST−T異常」、今年が「WPW症候群」の診断になっています。
当院の500Aの自動診断では「ST−T異常」と出ました。「もしや?」と思って、「筋電フィルター」や「基線フィルター」の
設定を変えてみると、「WPW症候群」の自動診断が出ました。
・・・うーーん、心電計ハード(&ソフト)の自動診断能力でなく、波形のフィルターの具合で診断が変化するのですね。
まあ、当たり前といえば当たり前。単に「この心電計の自動診断力は良い悪い」ということは言えませんねえ。
*H24/11/20追加:開発元が自律神経機能(心拍変動解析:HRV)ソフトを発売予定。
発売メーカーから文書でアナウンスあり。HRV(心拍変動解析=自律神経機能評価)ソフトを近日中に販売するそうな。
計測値は:
SDNN(RR間隔標準偏差)、CVRR(RR間隔変動係数)、rMSSD(連続した心拍間隔の差の二乗平均平方根)、
SDSD(RR間隔のSDの標準偏差)、pNN50(差が50m秒以上の隣接するRR間隔の割合)。
FFT処理で:Total Power、VLF(超低周波成分)、LF(低周波成分)、HF(高周波成分)、LF/HF(2つの比)。
ネットで検索すると、 http://www.qhrv.jp/dt_hrv_jp.htm などいろいろと情報がありますね。
オプションとしては3万円で販売だそうな(CD-R、セキュリティーキー付き)。
保険請求できませんが、診療上、そして臨床研究面でも強力なツールとなるかもしれません。
*H24/06/20追加:Late Potential(加算心電図による心室遅延電位測定:LP)測定機能を当院は追加導入。
事前予約していたLPソフトが当院に届きインストールしました。インストールは極めて容易。10分以内で終了。
新規のドングル(ソフト認証USBキー)もソフトに同梱しており、今までのドングルは販売元に返送する形になります。
LP・・・平成24年4月から点数200点で新規保険収載。肥大型心筋症・拡張型心筋症・陳旧性心筋梗塞・不整脈例などで、
ハイリスクかどうかをECGで判定する一手段です。メーカーのHPは http://www.pc-ecg.com/vlp/index.html
今までは測定機器が1台100〜数百万円したのですが、新規購入なら50万円以下(追加とすれば、35万円)で購入できるとは
驚きです。おまけに、面倒なフランク誘導でなく通常の12誘導からもLPを測定できるのも特筆すべきことだと思います。
ソフト同梱の「簡易マニュアル」は必要&重要な内容の記載があり、内容としては十分でしょう(本当は、技術的なデータも
公表していただけるとありがたいところです)。
※基礎心疾患をお持ちの方や原因不明の失神例などで、LPを(定期的に)測定する意義は大きいと思います。
ただ、35万円/保険点数200点=かなりの例数をこなさねばならないのでコストパフォーマンスでは???です。
しかし、リスキーな心疾患をフォローしている循環器専門医療機関なら、設置しておいてよいのかもしれません。
※(比較的)安価にLP測定機器を購入できることになります。LPが研究段階であった過去と異なり、さまざまな手法で
心機能・病態を正確に把握できる時代になっています。基礎心疾患の方々を多数フォローしている施設では
このLPソフトを使用することで、優れたリサーチができるかもしれません。
※LPは、臨床研究めいたところがあり、まとまった教科書・成書はありません(あるなら教えてくださいな)。
ネット検索では学会地方会レベルの情報は手に入ります。また、ネットで探した中で、たいへんありがたく思ったのは、
「日本心電学会」の検索ページです。右上の”検索”で”late potential”などのキーワードで、1986年頃からの
研究発表や総説がPDFファイルで閲覧できます。「日本心電学会」は太っ腹です。ありがとうございます。
皆様も良い資料がありましたら教えてくださいな。
*H24/05/01追加:心電図自動解析(コンピューター診断)について記載する・・・使えます。
本ソフト(本機)は心電図の自動解析(コンピューター診断)ができます。そして設定により診断結果の表示オン、オフもできます。
循環器専門医にとっては(ほぼ)不要の機能ですが、「診断能力はどのくらいかな?」と気になったので、診断結果の表示オンで
1年ほど使用してみました。気になる診断能力ですが・・・十分、使えます。PAC、PVCの診断はもとより、心房細動などの
判定もキッチリです(心筋梗塞の急性期の診断もできてました←できないと困る)。ちょっとビックリしたのは、
「陳旧性の下壁梗塞例でQ波がはっきりしない=一見正常例」でも診断できていたことです。開発元のHPでは、
独自のアルゴリズムで心電図判定をしているとのこと。通常使用で、この自動診断能力なら便利ですね。なお、
ソフト内部を見ると診断名には新しい疾患である「ブルガダ症候群」なども入ってました。
もちろん、「DDDペースメーカー例で自己脈が混じっている」、「体動で基線がブレ気味」などでは、正しい自動診断は不可能です。
注)不整脈例で、10秒取っての自動診断と1分取っての自動診断では診断結果が異なることがありました。
サンプリング間隔の問題でしょうか?この辺は難しい問題ですね。
注)20年ほど前(当然、ECG 500Aではない)、「f波が小さい心房細動+完全房室ブロック+rate 40/分の心室調律(←危険)」を
「洞調律+完全右脚ブロック(←正常範囲)」という自動診断していたのを見たことがあります。複雑で生命に危険が及ぶ
状態で、自動診断はしばしば診断間違いをする印象です。「医師による確認」が必須ですね。ポイントとして、
自動診断名が3つ以上並んだ場合、自動診断がキチンと解析できずシドロモドロにイイワケを状態が多いです。
自動診断名が3つ以上並んだ場合、自動診断が間違っている・危険な状態、も考えましょう (^_^)。
*H24/02/20追加:開発元が「加算平均心電図による心室遅延電位測定」機能の追加のアナウンス
加算平均心電図の測定は、生命予後推定の一助になり、治療法の選択のめやすにもなります。
多分、オプションで追加料金が発生するでしょうが、循環器専門医としてはぜひとも欲しい機能です。
おもわずヨダレが出る、ないし感激の涙を流すアナウンスです。
また、専門医でなくても加算平均心電図でハイリスク所見があれば専門医への紹介を考える、ということもあるでしょう。
解析ソフトが追加できるパソコン心電計ならではの話ですね。ソフトの発表が待ち遠しいです。
*H23/09/20追加:500A製造の三栄メディシスのユーザーフォーラムに登録した
三栄メディシス http://www.pc-ecg.com/ のユーザー用のユーザーフォーラムに登録しました。パスワードで同内に入れます。
フォーラム内は、ブログ形式でFAQやソフトのバグ情況(マイナーな使用法でのトラブル回避方法など)などの
情報が発信されています。
フクダ電子や日本光電などと異なり、500Aの営業所が各県にはないので万一のトラブル発生時にどうしよう、、、とも
思っていましたが、ここで情報が得られます。というか、電極類のパーツは同社から通販購入できるし、本体自体は
上記のように稼動部がなく故障も発生しにくいでしょう。最新情報も得ることができます。
・・・使用中の安心感が増しました。
*H23/07/20追加:(擬似)マスター負荷試験を実施。
ご高齢の方で「労作時に息切れ・胸部不快感〜異常感」を訴える方は多いです。肺疾患のためか、それとも
狭心症のためか確認するには運動負荷を行い、その前後で心電図を取り心電図変化を確認するのが有用です。
しかし、トレッドミルはご高齢の方には実行が困難(足下のベルトが強制的に移動するのに追従するのは大変)。
エルゴメーターも「胸に電極をつけての自転車乗りは初めてで緊張」〜「そもそも自転車に乗ったことがない」と
いうことで実施しづらいこともあります。そこで、ご本人のペース(+早めに)でマスター台を昇り降りしてもらい、
その前後のECGを500Aで取ってみました。
結果、運動直後でもECG基線のドリフトは少なく(500Aにはドリフト抑制機能あり)、十二分にECG評価が
できるものでした。
なお、製造元では複数心電図のViewerを開発中です。
H23/07/16:四肢電極のプラスチック部分が割れてしまった
平成22年末に500Aを購入し、ほぼ毎日使用。使用7ヶ月めの今月、通常通り、ECGを取ろうとしたら、左手誘導部分の
プラスチック部品が割れてしまいました。通常通りの使用で床に落としたわけでもないのですが、、、。
でも、スペアがあったのですぐに交換してスムーズに使用できました。
・・・初期不良かしら(実は、購入後に製造元から塩化銀電極使用の四肢誘導電極が無償で送られてきました。
初期は通常の銀色ステンレス電極だったのを、改善したとのこと=それでスペアを持っていたわけです。
スペアがない場合でも、電極をバンソウコウなどで固定して臨時的に心電図を取ることは可能でしょう)。なお、
数年にわたって 心電計を使用していると、胸部電極のゴム部分の劣化して使用しにくくなったり、落として
四肢電極を破損したりすることがあります。製造元から電極をパーツとして即納で購入できますから、
数年後でも安心ですね。
*H23/04/30追加:500A製造メーカーの三栄メディシスが、販売価格を14万8千円に改定(発売前は39.8万円の予価でした)。
開発元のブログにあるように、従来の”ペーパー式心電計が消えるのは時間の問題”かもしれません。
なお、安価で高性能のRS_Baseとの完全対応を同社のブログ内でアナウンスしています。
|